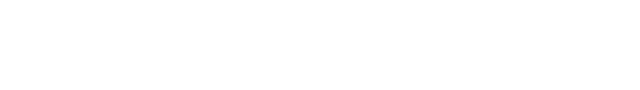小児眼科
子どもの近視
弱視の治療は、視力の成長を妨げる原因を取り除いて、見える力を獲得することです。視覚の感受性は、生後より1歳半頃までが最も高く、それ以降はゆるやかに下っていって、8歳~10歳ころまでがリミットだと言われています。

弱視には大きく分けて以下の4つの原因があります。
1 屈折異常弱視
高度の屈折異常(遠視や乱視、近視のこと)が原因です。常にぼやけた状態でしか見えないので、視力が発達しません。
治療は適切な眼鏡をかけて、両眼ともピントが合う状態にすることです。
2 不同視弱視
右眼と左眼の屈折の差が大きいため、見えやすいほうの眼を使い、見にくいほうの眼を使わないことが原因です。
治療は適切な眼鏡をかけて、両眼ともピントが合う状態にすることです。
見えにくい眼でみる訓練(アイパッチなど)をすることもあります。
3 斜視弱視
斜視になっている眼では眼の中心部にまっすぐ光が入らず、視力が育ちません。
治療は斜視を治す手術をすることです。弱視が関係している場合は眼鏡での治療を行います。
4 形態覚遮断弱視
先天白内障や眼瞼下垂など視力の発達時期に網膜に光が届かなくなることが原因です。
手術などの治療が必要になることがあります。
弱視治療にとって大事なことは、タイムリミットがあり、だいたい10歳くらいまでにしかできないということです。できるだけ早い時期にみつけて、適切な治療を開始することで、子どもの視機能を最良の状態まで育てることができます。
お子様の視力の問題に早くに気付いてあげるためには
子ども自身が「見えない」といって訴えることはありません。子どもは、自分の見え方以外の見え方を知らないですし、自分の見え方が当たり前と思って過ごしているからです。ご両親など身近な方が下記のようなことに気付いたら、早めに眼科専門医を受診することをお勧めします。
-
- 目を細めて見ていることがある
- 頻繁に目を触ったり、こすったりする
- 絵本、テレビ、タブレットなどに顔を近づけて見ている
- ものを見る時に横目になる
- 目が光っているように見えることがある
- 片目を隠すと不安な様子になる、嫌がる
※当院では国家資格を持った視能訓練士が大切なお子様の視力検査を担当いたします。